阪神淡路大震災(1995.1.17)まとめ
1995年1月に発生した阪神淡路大震災について、
災害の規模と、震災によって生じた影響についてまとめます。
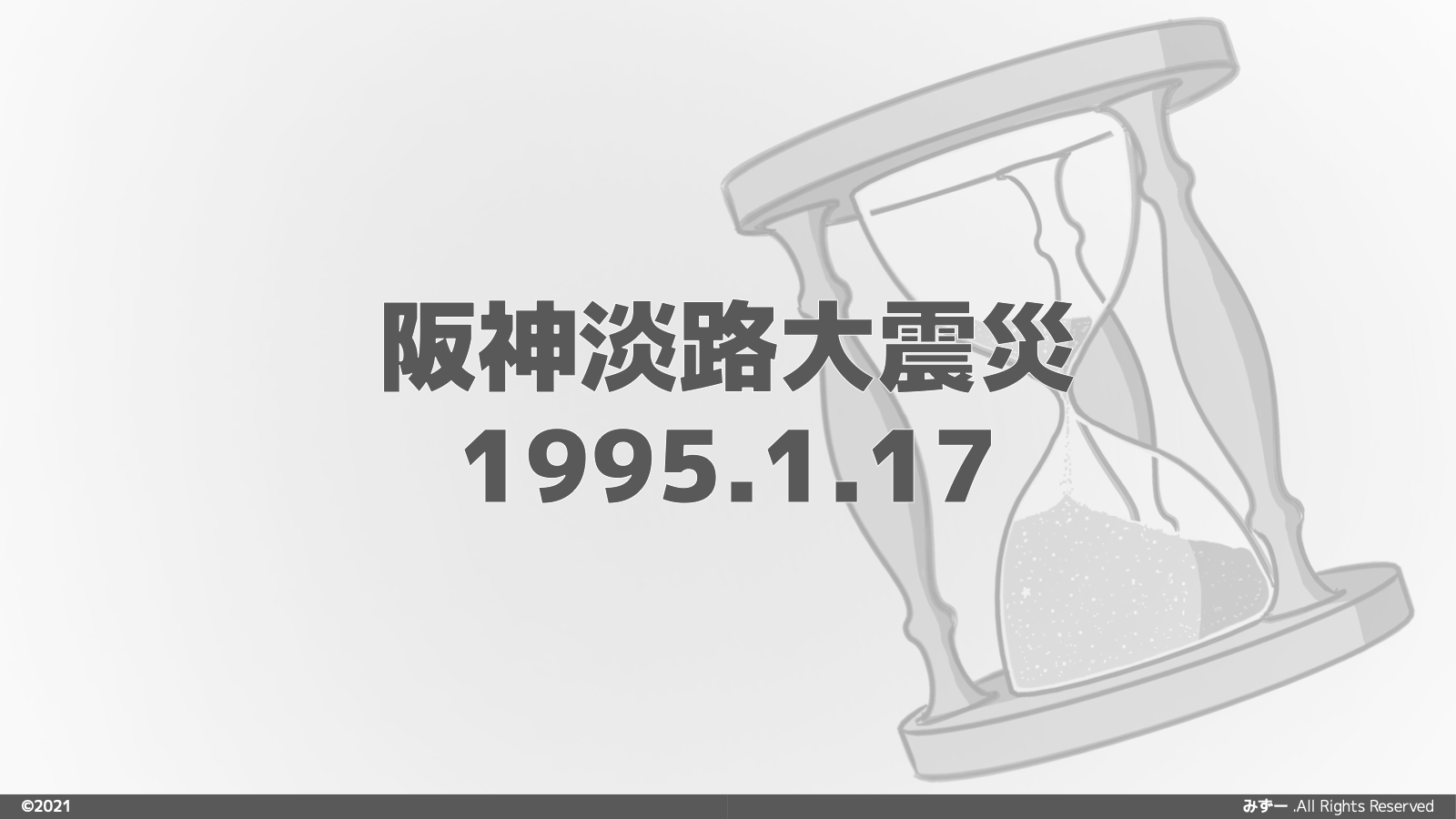
- 気象庁|「阪神・淡路大震災から20年」特設サイト
- 気象庁|「阪神・淡路大震災から20年」特設サイト
- 気象庁|地震予知について
- 建築:住宅・建築物の耐震化について - 国土交通省
- 地震のたびに強くなってきた耐震基準。旧耐震と新耐震をおさらい | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト
- カセットコンロ・ガスボンベの規格 | 埼玉越谷 保険代理店 株式会社しんせい保険サービス
- 兵庫県弁護士会とは 火災保険および火災共済の現行地震免責条項に関する提言 兵庫県弁護士会
- 水栓レバーの話|朝日設備工業株式会社|岐阜市|給排水衛生設備工事・空調設備工事・水道施設工事・機械器具設置工事
- 兵庫県南部地震 - Wikipedia
- 阪神・淡路大震災 - Wikipedia
- 地震予知 - Wikipedia
阪神淡路大震災
名称
「阪神淡路大震災」と呼ばれる災害は、火災などの二次災害も含めた包括的な名称
です。
地震のみについては「兵庫県南部地震」と気象庁が命名しています。
地震の規模
兵庫県南部地震の概要については以下です。
| 名称 | 兵庫県南部地震 |
| 発生時刻 | 1995(平成7)年1月17日 5時46分ごろ |
| 震源地 | 淡路島北部 |
| 緯度 | 北緯 34°36’ |
| 経度 | 東経 135° 2' |
| 最大震度 | 7 |
| マグニチュード(M) | 7.3 |
| 深さ | 16km |
| 観測範囲 | 東北地方南部から九州地方 |
各地の震度(震度4まで)
| 震度 | 地域 |
|---|---|
| 震度6 | 神戸 洲本 |
| 震度5 | 京都 彦根 豊岡 |
| 震度4 | 奈良 津 敦賀 福井 上野 四日市 岐阜 呉 境 高知 津山 多度津 福山 徳島 岡山 高松 大阪 舞鶴 姫路 和歌山 *加西 *相生 *南部川 *坂出 *多賀 *美方 *高野山 |
*印は気象官署以外で気象庁が観測した震度4以上の観測点です
被害状況
人的被害
| 死者 | 6425名 |
| 行方不明者 | 2名 |
| 負傷重症者 | 8763名 |
| 負傷軽症者 | 35009名 |
| 負傷者合計 | 43772名 |
住居被害
| 全壊 | 110457棟 |
| 半壊 | 147433棟 |
| 一部破壊 | 230332棟 |
| 合計 | 488222棟 |
インフラ被害
| 文教施設 | 941箇所 |
| 道路 | 10069箇所 |
| 橋梁 | 320箇所 |
| 河川 | 430箇所 |
| 崖崩れ | 378箇所 |
| ブロック塀等 | 1480箇所 |
ライフライン被害
| 水道断水 | 約130万戸 |
| ガス停止 | 約86万戸 |
| 停電 | 約260万戸 |
| 電話不通 | 30万回線超 |
| 火災 | 285件 |
震災により影響を受けたもの
建築基準
1978年に発生した「宮城県沖地震」を契機に、1981年に「新耐震設計基準」が導入されました。
阪神淡路大震災では、この耐震基準を満たしていたかどうかで被害の状況が大きく異なっており、
新しい耐震基準の重要性を改めて気づかされることになりました。
阪神淡路大震災以後は、1995年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定
され、
耐震基準を満たした建物へ改修するよう法律で促すようになりました。
地震の観測方法の変更・震度階級の改定
阪神淡路大震災時点では、体感による計測や周囲の状況(物が落ちる)などでの観測を行っていましたが、
1996年4月以降は、人による観測を廃止し全面的に計測震度計(機械)による自動観測を開始
しました。
震度速報の発表が遅れていたことへの課題も、これにより解決されました。
震災時は現在のように、震度計を設置した観測所が多くなかったため、
地域によっても発表される震度と揺れの大きさが一致していないことも明らかになりました。
震災後は観測所を増やし、現在の市区町村単位での発表が可能となっています。
震災当時は8段階しかなかった震度階級の見直しも行われました。
震度5と6には、同じ震度でもバラつきがあるとして、
それぞれを
「震度5弱・5強」「震度6弱・6強」と細分化し、1996年に全10段階に改定されました。
地震予知
地震予知とは「時間」と「場所」と「大きさ」の3要素を正確に予測するものを指します。
兵庫県南部地震の地震予知は成功しなかったため、地震予知研究などに批判が高まりました。
震災後の国策の見直し建議では「いまだに地震予知は確立されていない」として、
予知に対する手法が確立されていないという立場が明らかになりました。
その後「地震予知」という言葉を使うことに対しては、各所で見直しが進められています。
カセットコンロの規格の統一
震災発生当時、ガスが止まってしまった地域では、支援物資としてカセットコンロが避難所に届けられました。
しかし当時はカセットコンロの規格は統一されていなかったために、
ボンベとコンロの組み合わせが異なると使用できないといった不便が生じました。
1998年にJIS規格(日本産業規格)が見直され、コンロとボンベは他社でも組み合わせられる
ようになりました。
ただし、他社のボンベとコンロを混ぜることを企業側は推奨していないので、緊急時のみにした方がいいかもですね。
火災保険と地震保険
地震によって発生した火災は、火災保険に加入していても保険会社が責任を負わないとした保険が多いために、
阪神淡路大震災で火災保険の適用対象になった事例は多くありませんでした。
それにより
震災以後は、地震保険に注目が高まりました。
水道の下げ止め式の普及
阪神淡路大震災では、水道のレバーに物が落下し水道が出っ放しになる事例が発生しました。
欧米での普及の流れもあり、2000年のJIS規格統一以後、水道は下げると止まるレバーに一本化
されました。
おわりに
執筆現在、阪神淡路大震災からは26年の月日が流れました。
被害にあわれた方へのご冥福をお祈りいたします。
